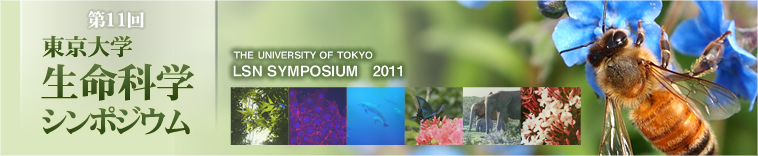
ポスター発表される方へのご案内
平成21年5月1日(土)、安田講堂及び工学部2号館にて、第10回東京大学生命科学シンポジウムが開催されました。昨年より、生命科学の、教育支援ネットワークと研究ネットワークという二つの組織が一つになり、生命科学ネットワークとして、総合的なシンポジウムの運営を行うことになりました。
これまで行ってきた生命科学に関するシンポジウムを合わせると、東京大学の生命科学シンポジウムは今回で第10回目を迎えます。生命科学ネットワークは、生命科学に関わる学内16部局で構成され、研究者交流や教科書作成などの活動を通じて、研究教育支援に取り組んでいます。
当日は五月晴れの空の下、高校生から60歳以上の方まで、学内外あわせて、例年を超える906名の参加があり、どの会場も賑わいを見せました。シンポジウムは、講演の部・部局紹介ブース(安田講堂)、ポスターセッションの部(安田講堂、工学部2号館フォーラム・展示室)から構成されました。講演の部は濱田総長の挨拶に始まり、本シンポジウムが「生命科学を学ぼうとする学生の皆さんへの進路選択ガイダンス」「研究者同士の異分野交流の場」「一般の皆様に生命科学への関心を持っていただく場」という目的を持っていることや、多様な生命科学研究の最先端を行っている本学において、生命科学全般を横断する形での集まりは他にはなく、東京大学生命科学ネットワークだからこそ開催できる催しであることを、お話されました。

開会の挨拶をされる濱田総長
今回の講演の部では、生命科学ネットワークを構成する16部局のうち8部局から講演者の先生にお越しいただき、医療最前線や遺伝子・ゲノムの話題、電子物性や材料科学と生命科学の関わりのお話、生命に関わる法律や哲学の問題、そして昆虫や海にすむ微生物を対象とした研究について、ご講演いただきました。
参加者アンケートでは「最先端に触れることができ、勉強になりました」との意見が多く寄せられ、非常に広範な生命科学のエッセンスを楽しんでいただけたように思います。最後に、山本生命科学ネットワーク長の、「次回は、今回講演のなかった8部局の講演を行う予定ですので、またいらしてください」との言葉と共に、講演の部は盛況のうちに終了いたしました。

講演の部閉会の挨拶をする
山本ネットワーク長
安田講堂ロビーには、16部局の紹介ブースが設置され、パンフレットや成果物集などが展示されました。特に学生の方々から、「大学院進学の参考になりました」という感想が寄せられました。用意したパンフレットの山がなくなってしまうブースが出るほど、賑わいをみせていました。

賑わう部局紹介ブース
今回初の試みとして、講演に加えて学内研究者・学生によるポスターセッションを同日開催いたしました。各部局から291題の演題登録があり、3つの会場のあちらこちらで活発な議論が繰り広げられていました。アンケートにも「とてもいい刺激になりました」「様々な研究分野を見ることができて興味深かったです」との意見が寄せられ、このシンポジウムをきっかけに異なる分野、異なる所属の研究者・学生間の交流の芽が生まれたものと感じました。

ポスターB会場
(工学部2号館フォーラム)
午後6時からは、生協第二食堂において懇親会が開催され、歓談に華が咲き、盛況のうちにシンポジウムは終了しました。
アンケートでは、回答者の82%が「次回もシンポジウムの企画を希望する」と回答され、概して満足していただけたと思います。ゴールデンウィーク期間中の開催だったにもかかわらず、多くの方にお越しいただき、準備をしてきた私たちも、本シンポジウムが生命科学研究者間の横断的な交流や、学生の進路選択、一般の方々に関心を持っていただく場として一助になったと感じ、大変うれしく思っています。
最後に、ご講演いただいた講演者の皆様、開催の準備にご協力いただいた研究機構支援課の皆様、シンポジウム実行委員長石浦章一教授と研究室の皆様、教養教育高度化機構生命科学高度化部門の教員の皆様に深謝いたします。